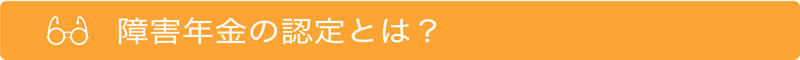
障害年金を受け取るためには、「障害認定日」において、一定以上の障害状態にあることが必要です。
この障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日、またはそれ以前でも症状が固定し、回復が見込めないと医師が判断した日になります。
また、障害認定日よりあとに状態が重くなった場合には、「事後重症請求」として申請することも可能です。
認定の審査はどうやって行われる?
障害年金の審査では、提出された診断書や申立書の内容をもとに判断されます。
そのため、「医師の診断内容」だけでなく、「普段の生活でどれくらい困っているか」を申立書などで具体的に伝えることがとても重要です。
例:「1人で買い物に行けない」「服の着脱に介助が必要」「疲れやすく仕事が長続きしない」など
→ 日常生活の困りごとをできるだけ詳細に書くのがポイントです。
等級のしくみ(1級・2級・3級)
障害年金の等級は、病名そのものではなく、「生活や仕事への支障の程度」で決まります。
1級(もっとも重い等級)
日常生活に常時他人の介助が必要な状態。ほぼ寝たきりやそれに近いレベル。
※就労していても支給されることがありますが、例外的です。
2級
日常生活に著しい制限がある状態。身の回りのことができても、社会生活が困難なことが多い。
うつ病、統合失調症、心疾患、難病などで該当することが多い等級です。
3級(※厚生年金加入者のみ)
就労に制限がある状態。軽作業などであっても安定的な就労が難しいと判断される場合。
身体障害(手足の一部の欠損・難聴など)や、軽度のうつ病などで認定されることがあります。
まとめ:大切なのは「病名」ではなく「生活への影響」
障害年金の認定は、「うつ病だから何級」「糖尿病だから対象外」といった病名では決まりません。
あくまで“生活や就労にどの程度支障が出ているか”で総合的に判断されます。
だからこそ、
「ちょっと働けているから無理かも…」
「病院に通ってるけど障害には当たらないかも…」
と思っている方でも、制度上は対象になる可能性があるのです。
ご相談は無料です
当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。
診断書の読み方や、ご自身がどの等級に該当する可能性があるかも一緒に整理していきます。
「自分が対象かも…」と少しでも思ったら、まずはお気軽にご相談ください。